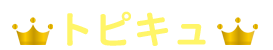南米ペルーにある有名な遺跡、「マチュピチュ」。
学校でも習う遺跡のため、名前を聞いたことがある方も多いと思います。
今や観光地としても有名な場所になってきましたが、マチュピチュはただの遺跡ではありません。
空中都市と呼ばれるほど標高が高い場所にあり、謎が多く残された遺跡なのです。
なぜ標高が高い場所に街を作ったのか?マチュピチュに残されている謎とは何か?マチュピチュの古代ミステリーに迫ります。
マチュピチュとは何?どの時代の遺跡?

マチュピチュは、インカ帝国の時代に作られた遺跡です。
インカ帝国とは、南米にあるペルーやボリビア・エクアドルを中心に発展した国。
そのインカ帝国には、いくつかの特徴があります。
- 文字持たない文明だった
- 石の精密な加工技術があった
- 水が流れる最低の角度を知っていた
- インカ道という道路網を作っていた
- 飛脚などを使い、広大な土地を統治するシステムがあった
文字を持たない文明だったため、インカ帝国時代の詳細は不明な部分が多くありますが、これらの特徴からインカ帝国は栄えたと考えられますね。
そんなインカ帝国時代に作られた遺跡がマチュピチュで、1450年代頃に建てられました。
場所はアンデス山脈にあるウルバンバ谷に沿った山の尾根にあり、その標高は2,430メートル。
富士山と比べると、6合目あたりの高さにマチュピチュの遺跡があることになります。
また、インカ帝国の首都クスコはマチュピチュよりもさらに標高が高く3,400メートルもあり、富士山と比べると8~9合目に都市が発展しました。
とても高い位置に街や文化を作り上げていったのが、インカ帝国なんです。
マチュピチュの遺跡は複合遺産だった!

ペルーにはインカ帝国時代の遺跡が多く残されています。その中でとても有名な遺跡が、このマチュピチュです。
遺跡ではありませんが、インカ帝国時代の首都であったクスコも、現在でも人が住んでいる街として有名ですよね。
この2つは、インカ帝国時代の大変貴重なものとして世界文化遺産に登録されました。
その後、マチュピチュは自然遺産としても登録されることになり、複合遺産となったのです。
マチュピチュはインカ帝国時代の遺跡として保存状態が極めて良いこと、そして周辺の自然環境や景観、動物や植物に絶滅危惧種もいることから、遺跡周辺の自然も含めて複合遺産として1983年に登録されました。
マチュピチュは現在多くの観光客が訪れており、遺跡の保護が難しくなってきているという話もあります。
世界遺産というだけではなく、どんな生活をしていたのか、なぜその場所に作られたのかなど多くの謎が残されているため、古代ミステリーやオーパーツ好きとしては、遺跡の保護も考えていく必要があるのかもしれませんね。
マチュピチュは石で作られた遺跡!作られ方が凄い!?

インカ帝国時代に作られた建物の多くは石で建てられたものがほとんどで、マチュピチュも石で建てられました。
しかし、マチュピチュは古代の技術とは思えないほど凄い技術が使われていたんです。
マチュピチュの遺跡では小さめの石を集めて接着剤のようなものでくっつけた建物もありますが、大きい石を積み上げた建物も多くあります。
大きな石を組み上げたものは石同士がピッタリとくっついているため、隙間がほとんどなく、カミソリ1本も入らないような精巧な積み方をしているんですよ。
こんな積み方ができるのは石を綺麗に均しているからなのですが、機械の技術がない時代に石を均す技術があったことが凄いですよね。
石はマチュピチュの石切り場から取られたと考えられており、石の採掘方法や石の均し方も判明しています。
しかし石を採掘するにしても、均すにしても1日で終わるものではないので、長い時間をかけてマチュピチュの遺跡を建てたということが分かりますよね。
マチュピチュの遺跡は、この石の組み上げ方だけが凄いわけではありません。
マチュピチュのあるペルーでは過去大きな地震が多く起こっていますが、マチュピチュはほとんど崩れておらず、大きなズレも確認されていないんですよ。
大きな地震にも耐えられる石の組み上げ方や均し方を当時の人が知っていたことは、本当に凄いことだと思います。
マチュピチュはなぜ標高が高い場所に作られたのか?

マチュピチュには謎が多く残されていますが、その中の1つ「なぜ標高の高い部分に都市が作られたのか」について考察していきます。
マチュピチュに限らず、インカ帝国は首都クスコを含め、とても標高が高い場所に都市や文化が発展してきました。
いったいなぜ、標高が高い場所に街を作ってきたのでしょうか。
マチュピチュが高い場所に作られた理由① 攻撃を受けにくい説
マチュピチュが高い場所に作られた理由として考えられるのが、標高が高いと攻撃を受けにくいということです。
特に山の頂上付近にある街や施設は、下から山を登って攻撃するか、周囲の高い山や空から攻撃をするしかなくなります。
周囲の高い山に関しては隣接していなければ攻撃しにくいですし、インカ帝国時代に空を飛んで攻撃をすることは考えにくいため、下からの攻撃を防ぐために高い場所に作ったと考えることができるでしょう。
マチュピチュが高い場所に作られた理由② 太陽神を祭った施設という説
攻撃を受けにくい都市作りの他には、宗教施設が考えられます。
インカ帝国は太陽神を信仰していました。
太陽神であれば、山の一番高い部分に宗教的な施設を作り、太陽を祭ることが考えられます。
古代に栄えた文明は天文的知識を持っていたと考えられる遺跡が多く見つかっているので、インカ帝国時代に太陽の動きをしっかりと把握し、太陽神を祭った宗教的施設を建てていても不思議ではありません。
マチュピチュには水路がある!?水源が分かっていない謎

マチュピチュの最大の謎ともいえるのが、「水源」です。
マチュピチュは、山の山頂付近に作られた遺跡でした。
多い時で700人以上の人が住んでいたと考えられているため、生活に必要な水や食料は欠かせないものだったでしょう。
食料はマチュピチュの遺跡に残されている段々畑で栽培されたと考えることができますが、水はどうやって確保していたのでしょうか。
古代文明が栄えてきた場所には、これまで大きな川が流れていることが多くありました。
それは、人にとって水は欠かすことができないものだからです。しかし、マチュピチュは山の山頂付近なため大きな川はありません。
また、隣接する山にも比較的大きな川はないため、水がたくさん流れてくるような環境ではないのです。
実は、マチュピチュには石で作られた水路が存在しているんですよ。
しかし、水路をたどっても水源には未だにたどり着けていないのが現状です。
遺跡を壊しながら探せば水源がわかるのかもしれませんが、貴重なインカ帝国時代の遺跡でもあり世界遺産でもあるため簡単に壊すことはできず、水源を探すことは今のところできていません。
今後もっと機械が発達することによって、マチュピチュの水源が発見されることを期待しましょう。
マチュピチュから人が消えた!?スペインの侵攻説の謎!

マチュピチュには、「人が消えた謎」があります。
「スペインが侵攻してきたので人がいなくなった」という説が有名なのですが、侵攻してきたという割には、マチュピチュの遺跡は攻撃された形跡が残っていませんでした。
マチュピチュは、インカ帝国時代に建てられた当時の原型が綺麗に残されたままの遺跡だったんです。
では、なぜマチュピチュに住んでいた人々は遺跡からいなくなったのでしょうか。
本当にスペインが侵攻してきたのであれば、降伏したか攻めてくる前に遺跡を捨てて脱出したと考えることができますが、本当にスペインの侵攻が理由だったのでしょうか。
マチュピチュは1450年に建てられたことが分かっていますが、その約80年後の1533年にはインカ帝国がスペイン侵攻によって滅亡しています。
インカ帝国滅亡までの間には伝染病を含め、病気が蔓延したりしてインカ帝国の多くの国民が亡くなっていました。
インカ帝国の人口の激減や伝染病、スペインの侵攻によって、マチュピチュの存在意義を失ったと考えることもできます。
マチュピチュから人が消えた本当の理由は未だに分かっていませんが、インカ帝国が滅亡したことが関係しているのかもしれませんね。
マチュピチュは何のために作られた遺跡なのか?

マチュピチュが何のために作られた遺跡なのか、に関しては2つの有力な説が存在しています。
一つは、王族や貴族のための避暑地。もう一つが神殿としての役割です。
どちらが本当の作られた理由なのかはまだわかっていませんが、有力視されているこの2つの説について紹介していこうと思います。
マチュピチュがなぜ作られたのか① 王族や貴族のための避暑地
マチュピチュの遺跡には、石で建てられた建物が約200戸あります。
その200戸の建物の多くは、王族や貴族とその使用人の住まいだったと考える説がありました。
マチュピチュには大きな建物があったり、宗教的施設があったりしていることから、地位の高い人が住む場所と生活を支えるための人が住む場所もあったと推測され、王族や貴族の別荘のような使われ方をしたと言われています。
別荘として王族や貴族が使用している時は約750名もの人が住んでいたと言われていますが、雨季や王族がいなかった時期は本当に少数の人しかいなかったという説もありました。
もし本当に王族や貴族が住んでいた場所なのであれば、インカ帝国が滅亡する寸前には王族や貴族も自由に移動することができなかったと考えられるため、マチュピチュから人がいなくなった理由にもつながりますね。
マチュピチュがなぜ作られたのか② 神殿としての役割
インカ帝国時代に信仰されていたのは、インティと呼ばれる太陽神でした。
インカ帝国には広大な土地があったため、各地に神殿が建てられたと言われています。その一つが、マチュピチュだと推測されました。
マチュピチュは北と南には大きな山がありますが、西と東は断崖絶壁になっており、太陽を観測するには適した場所です。
また、マチュピチュには皇帝が建てたと言われている「太陽の神殿」という場所がありました。半円の建物でできていて、夏至と冬至の日に差し込む朝陽の位置が計算された場所です。

太陽の神殿の他に「3つの窓の神殿」という場所もあるのですが、この場所にも夏至と冬至の朝に朝日が差し込む窓がありますね。

また、マチュピチュには一番高い場所に「インティワタナ」という日時計ではないかと言われる石が存在しています。

画像出典:Wikipedia
インティワタナというのは「太陽を繋ぎとめる石」という意味があり、時間や季節を知るためのものだったと考えられました。
これらのことから、マチュピチュは太陽神を祭る神殿だったのではないか、という説が生まれたのです。
マチュピチュの人々は、太陽の近い位置に神殿を作ることで太陽神への信仰を深めていったのかもしれませんね。
マチュピチュ遺跡から見える山にも遺跡がある!?

マチュピチュの写真を見ると、必ずと言っていいほど後ろに大きな山が見えます。
それはワイナピチュと言われる山で、現在入場制限がありますが入山することができる山ですね。
このワイナピチュにも、マチュピチュのようなインカ帝国時代の遺跡が残されています。
マチュピチュには太陽の神殿がありますが、ワイナピチュには月の神殿という場所があるんですよ。

画像出典:Wikipedia
月の神殿は、洞窟の中に存在している神殿。マチュピチュの人は、太陽と同じように月も信仰していたのかもしれませんね。
また、ワイナピチュの山は人の顔に見えるという噂もあります。
「ワイナピチュの写真を縦にすると口をあけた人の顔に見えてくる」、というものです。(見えますかね…?)
ただ人の顔に見えるというだけの話ですが、遺跡がある場所ということもあって、ちょっとしたミステリーですね。
【まとめ】世界中から人が集まるマチュピチュは魅力と謎が満載の空中都市!

世界中から人が集まる場所として有名なマチュピチュ。多くの観光客がマチュピチュを訪れます。
それは断崖絶壁に作られた綺麗な都市の光景だけではなく、多くの謎に包まれた場所という魅力があるからではないでしょうか。
なぜ作られたのか、どうして放棄されたのか、水源はどこなのか…まだまだ解明されない謎が残されていますが、現地に行った人の多くがマチュピチュから不思議な力を感じています。
不思議な力がある場所だからこそ、高い山の上に街が作られたのかもしれませんね。
そんな魅力のある不思議な遺跡・マチュピチュ。これからもっと謎が解明されていくことを期待しましょう!